昨今、人気のキャンピングカー。アウトドアだけでなく様々なシーンでの活用が現在注目を集めています。
- キャンピングカーの使われ方について知りたい
- キャンピングカーは災害時に役立つのか?
- 自治体やキャンピングカー業界の動向を知りたい
- コロナ禍でキャンピングカーの使い方に変化はあったのか?
この記事ではJAC公認オートキャンプインストラクターの筆者が、最近のキャンピングカー事情をご紹介します。
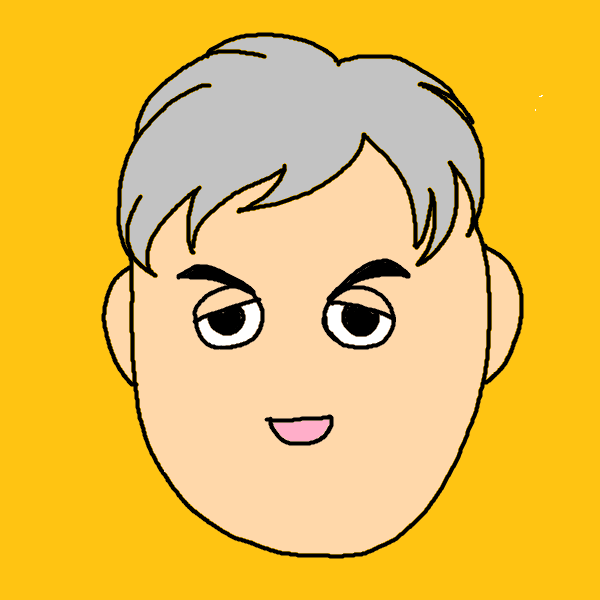
結論としてはキャンピングカーが様々な場面で役立っています
キャンピングカーオーナーが「災害時にも安心」と回答
日本RV協会が発行する【キャンピングカー白書】(2023年)によると、キャンピングカーオーナーの98.1%が「キャンピングカーは災害時にも役に立つ」と回答しています。
主な内容としては、以下のポイントが挙げられています。
- 避難所などに行かず空間(プライバシー)を確保することができる
- 電源、水などライフラインを確保できる
- 移動手段
と言ったように、キャンピングカーオーナーが自分で使っているからこそ自信を持って「災害時にも役立つ」と実感しています。
車中泊歴30年近いけど、以前は「貧乏くさい」「それなら行かない方が良い」など散々バカにされたけど東日本大震災、とどめにコロナで世間の目が変わった。
道の駅での車中泊の是非と問われたりもしたけど現在はマナーの悪い人は極々一部で殆ど見かけない。
災害時ペットを連れて避難に備えもなると思う pic.twitter.com/8nWszQEnZw— ムギぺた (@mugimugimix) July 1, 2023
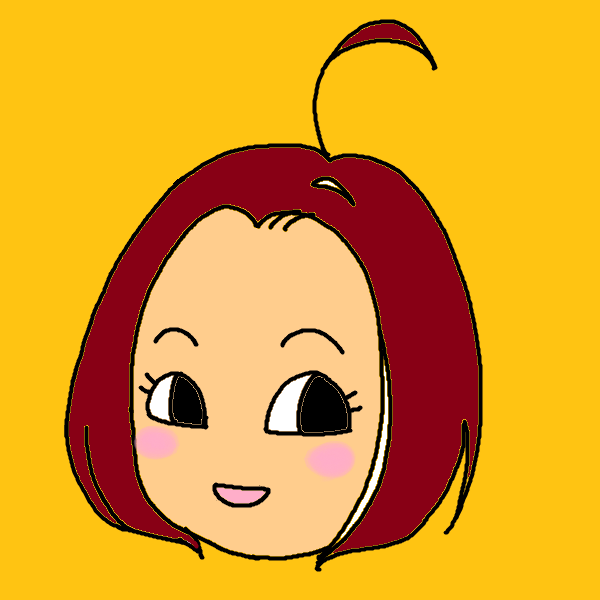
特にペットと一緒に避難できるのは大きなメリットですね
各自治体がキャンピングカービルダーと提携を開始
災害時にキャンピングカーを利用できるように各自治体がキャンピングカービルダーと協定を締結している動きが見られます。
【ナッツRV】「災害時における提供に関する協定書」の締結
キャンピングカービルダー最大手の【ナッツRV】は、災害時にキャンピングカー提供を行える協定を福岡県宗像市と締結しました。
キャンピングカーは設置から運用まで時間がかからない、移動が可能、プライバシーが確保できるなど、その特性を活かした災害発生時の支援や被災地の復興サポート等に活用できます。
【ナッツRVプレスリリース】災害時にキャンピングカー提供を行える協定を福岡県宗像市と締結
【ダイレクトカーズ】地方自治体と災害協定を締結
三重県を本店とするダイレクトカーズでは南海トラフ地震に備えて複数の地方自治体と災害協定を締結しています。
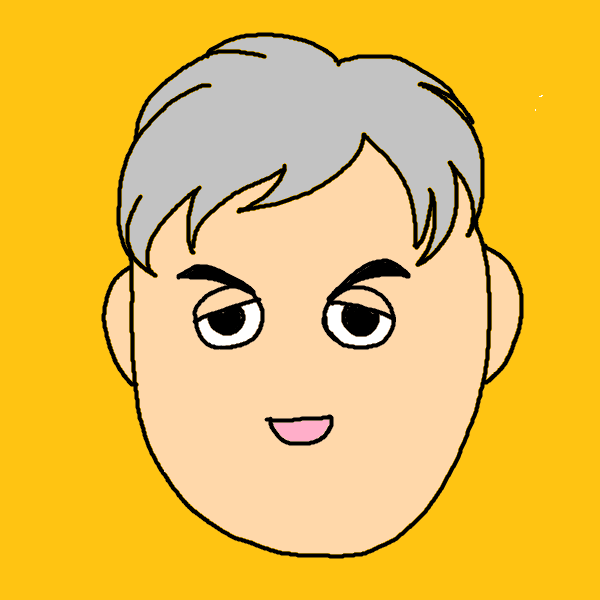
こういった場面で社会貢献されているビルダーは本当に尊敬しますね
コロナ禍でキャンピングカーを隔離場所として利用
2019年からのコロナ禍で、キャンピングカーの役割も少しづつ変化してきています。
レジャーについては、人が多く集まる場所へ行くことが敬遠された結果、家族でキャンピングカーで三密を避ける場所へ旅行したり、ホテルに泊まらずに車中泊やキャンプに出かけたりという報道も多く見かけるようになりました。
極端な例かもしれませんが、コロナ禍で家族4人で出かけるために、1,000万円を超えるキャンピングカーをご購入されたご家族もいると情報番組で見たこともありました。
また感染症が発生した場合は、自宅隔離でなく、キャンピングカーで自主的に隔離するなどの対応をしている方も見えました。SNSではキャンピングカー内でリモートワークするといった方々も見かける様になりました。
お疲れ様です。
目指せ週休3日の水曜でしたが普通に仕事しました
そして娘がコロナ発症のため私はキャンピングカーに自主隔離2日目
とりあえず私もお妻も発症なし
娘の氷枕のために冷凍庫の氷が無くなったのでコンビニで氷を購入したら250円くらいした😱
発症はしないが発狂しそうになった😭 pic.twitter.com/1hboR5Ax66
— GB (@GB43548759) June 7, 2023
キャンピングカーによる防災支援(能登半島地震)について
 キャンピングカーショー2025での「キャンピングカーと防災」トークショーでもキャンピングカーの防災における有用性が語られました。
キャンピングカーショー2025での「キャンピングカーと防災」トークショーでもキャンピングカーの防災における有用性が語られました。
ご自身でもキャンピングカーを使用している女優の田中美奈子さんは「有事の時に避難所に代わる。避難シェルターになる」という意識を持っているようです。
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)・明城徹也さんによると、実際の災害地で起きていることとしては、以下のことが挙げられました。
・被災者がどういう状況か分からない
・自治体職員や支援者が住む環境がない
・電気・水道・トイレなどライフラインが遮断されている
・防犯上、女性の支援者を被災地に送れない
こういったことを少しでも解消するためにキャンピングカーがあると本当に助かるとのこと。
やはりベストはご自身でキャンピングカーを所有していると、避難所に行くことなく子供やペットがいても安心して過ごすことができるとおっしゃっていました。
2024年1月に起きた能登半島地震で、実際に支援に向かった一級防災管理士の大塚和典さんからは「被災地の役所の会議室も廊下も職員でいっぱいで、職員が足を伸ばして寝れる状況になかった。」との悲惨な状況が伝えられ、
災害発生後にいち早く日本RV協会に支援要請し、自治体の職員用に60台以上のキャンピングカーがJRVAから提供されました。支援する側の職員はキャンピングカーで過ごすことに恐縮されたようですが、「そこで休んで明日の支援の活力に」という思いを伝えられると、本当に感謝されたようです。
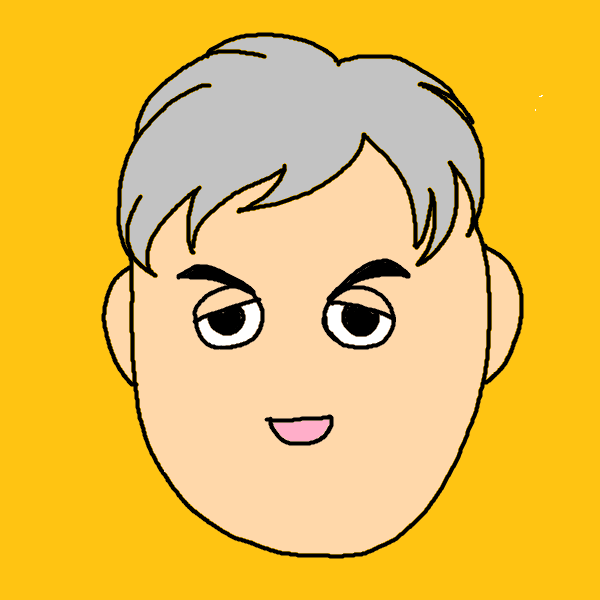
実際に被災地支援に行った方からのお話をお伺いし本当に考えさせられました
石川県 能登半島地震初動対応検証
○独立した危機管理部の設置
○2次避難運営マニュアル整備
○デジタル技術の活用
○支援職員等の宿泊施設の確保
・キャンピングカー
・トレーラーハウス#初動対応能登半島地震の初動対応検証 県が中間報告示す|NHK 石川県のニュース https://t.co/tabYgGZIsb
— FukushimamanZ (@FukushimamanZ) January 25, 2025
初心者のための防災講座(災害に備えての準備)
災害ボランティアにも参加している防災士の高木一彦さん(NPO法人日本防災士会)によると、「災害の際、避難所はプライベートスペースが確保できないためキャンピングカーが役に立つ。災害大国の日本においてはキャンピングカーと防災の親和性がある。」とおっしゃっています。
また災害の準備として以下のような準備をしておくといいです。
・災害用トイレを最低でも3日、余裕をもって2週間分準備する
・飲料水を確保しておく
・食材の備蓄をしておく
防災食があると便利だが、普段から食料など今までご自身で使っているものを定期的に回しながらローリングストックしておく
・ポータブル電源があると便利
・薬を切らさないために保管しておく
一般車での車中泊について(カーネル・編集部より)
2016年に発生した熊本地震で車中泊避難が注目されました。被災時にはグランメッセ福岡の駐車場に1000~2000台の車中泊をする車が集まったそうです。
その熊本地震の際に車中泊をしていた50代の女性がエコノミークラス症候群で亡くなってしまったという悲しい事例も発生しています。やはり足が曲がった状態で就寝すると血の流れが悪くなる恐れもありますので、車中泊をする際は気を付けたいですね。

そういった点からも一般車は横になって寝ることは難しいと考えられがちですが、一般車でも問題なく車中泊できるポイントがあります。
できる限り以下の状態を確保することが望ましいです。
・足を伸ばして寝るスペースを確保する。目安としてはご自身の身長+10~15センチの長さ、幅は一人当たり55センチ以上
・車中泊三種の神器(マット、寝袋(または布団)、ウインドウシェード)を準備する
・車はロック(施錠)できるので、車中泊は女性を優先する
 例としてランドクルーザー250の助手席では、シートを倒した状態で135センチしか確保できないので大人が就寝することは難しいです。
例としてランドクルーザー250の助手席では、シートを倒した状態で135センチしか確保できないので大人が就寝することは難しいです。
ランクルのラゲッジスペースで後部座席を倒した状態であれば195センチの広さを確保できますので、180センチ程度までの大人は就寝できることになります。
「家族何人で車中泊するのか?」などご自身のご家族構成や避難人数を考慮して、一度車中泊をすることを想定して準備してみてはいかがでしょうか。
家族全員が車中泊できないのであれば、プラスアルファでテントなどの準備も必要になります。できれば平時に実際に車中泊をしてみるといいと思います。
※ジャパンキャンピングカーショー2025のカーネル・編集部ワークショップでの取材を元に一般車での車中泊する上でのポイントについて解説させていただきました。
キャンピングカー+防災備蓄品準備で災害に備えた体制を整えておくと、いざというときに困らなくて済みます。この機会に一度ご家族と話し合ってみてはいかがですか。
以上、今回は防災関連情報と「見直されているキャンピングカーの有用性」についてお伝えさせて頂きました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
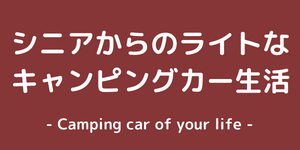
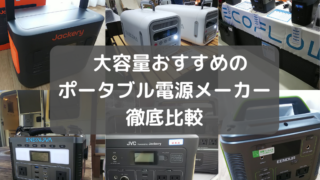

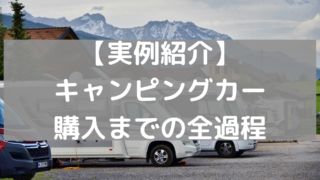
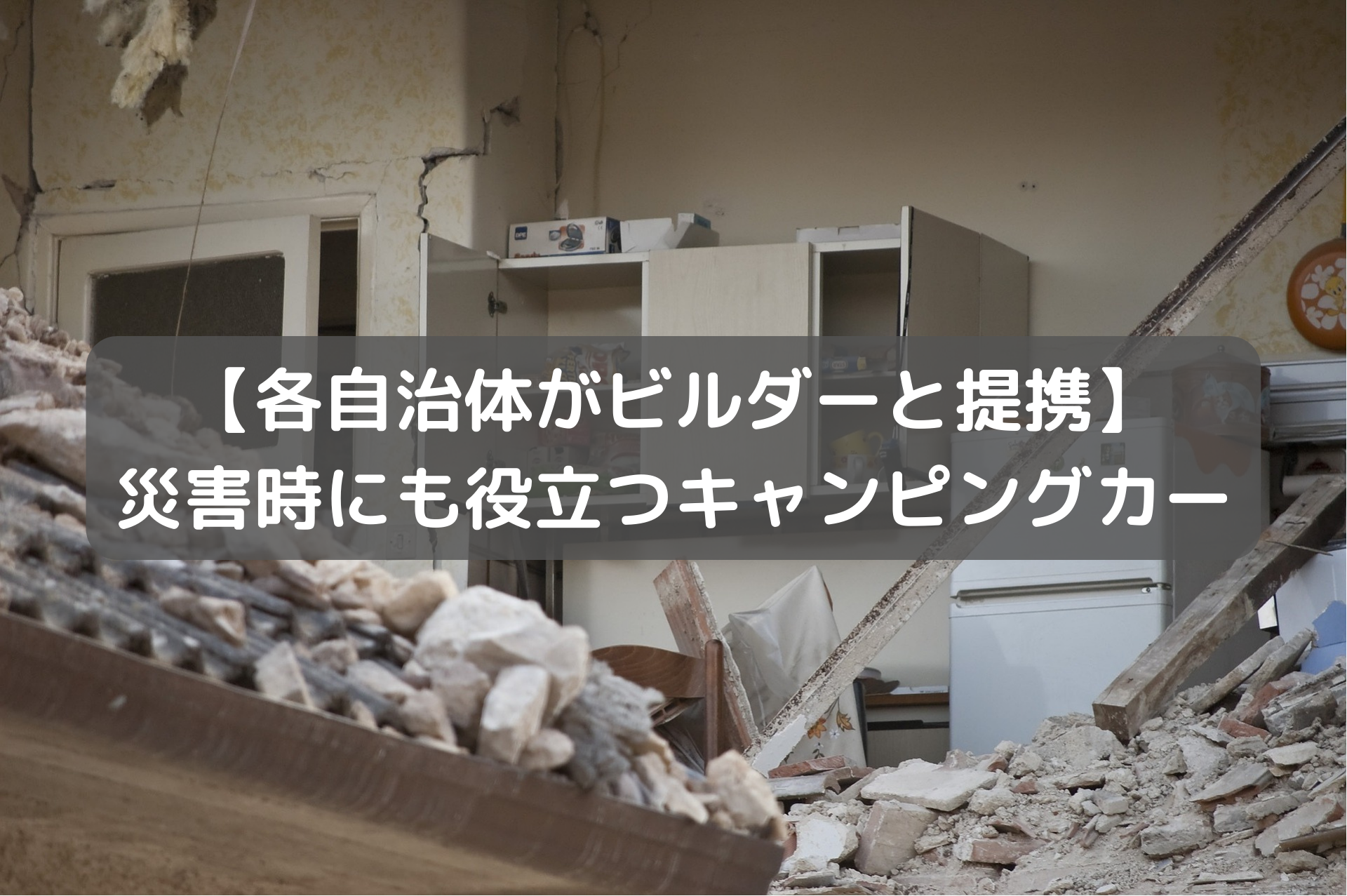


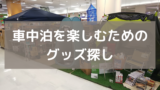


コメント